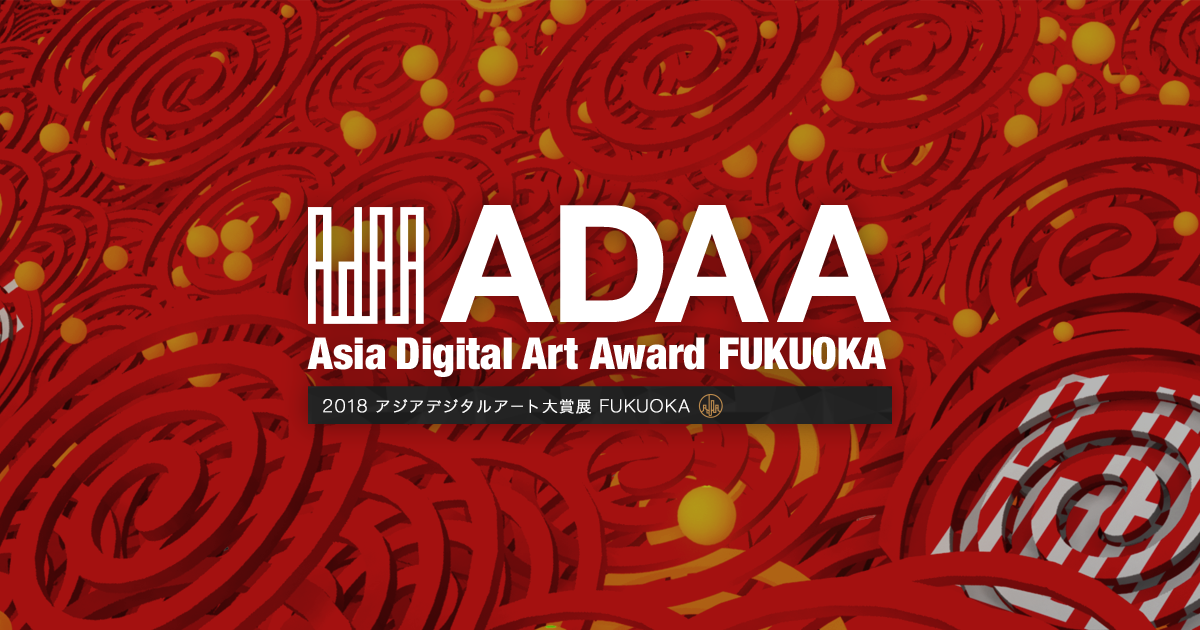古市研究室 新着情報
What's up!, the latest news at Furuichi Lab.
- 詳細
NHK総合の番組「歴史探偵 黒船来航」に,日本大学生産工学部の古市昌一教授(モデリング&シミュレーション),国際関係学部の淺川道夫教授(軍事史),生産工学部の粟飯原萌助手(シリアスゲーム),生産工学研究科博士後期課程学生川上智君(現役海上自衛官)が出演します.番組では,幕末1854年に2度目に江戸湾へ来航した黒船と,江戸防衛のために海上に築城された6つのお台場の砲台を舞台とし,もしその時に日米交渉が決裂していたらどうなっていたか?,これを日本大学の4名の各分野専門家が明らかにします.見どころはたくさんありますが,この番組のために新たに粟飯原萌先生が開発したウォーゲーム PERULI を駆使し,近田アナウンサーによる戦況実況を交えての議論にご着目ください.
- 番組名:歴史探偵 #2黒船来航
- 放送日時:2020年3月25日(水)総合 夜22:30~23:15
- ※地上波に加えて,日本語の国際放送及びNHKプラスによるインターネット配信で視聴できます
- ※番組HP https://www6.nhk.or.jp/nhkpr/post/original.html?i=22720/
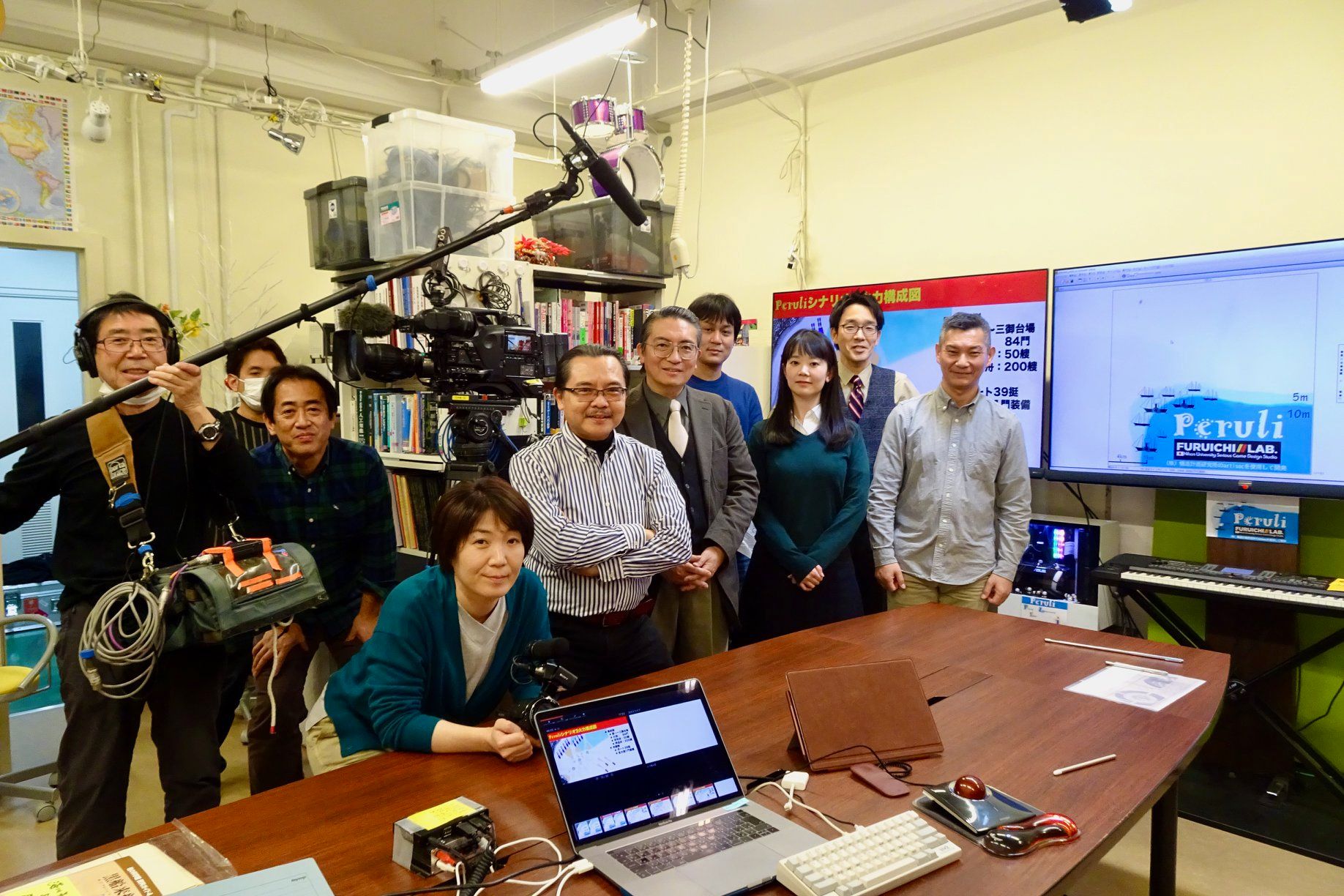
歴史探偵は2019年12月から新たに始まったNHKの歴史番組で,「歴史探偵#1本能寺の変」が次の通り再放送されます.この番組でも日本大学生産工学部の古市昌一教授(モデリング&シミュレーション)と生産工学部の粟飯原萌助手(シリアスゲーム),生産工学研究科博士前期課程学生高橋昂大君が出演し,明智光秀の軍勢が丹波亀山城から京都本能寺の行軍ルートを解明する部分で出演しています.黒船来航と併せてご覧ください.
- 番組名:歴史探偵 #1本能寺の変
- 放送日時:2020年3月23日(月)総合 午前0:40~01:30
- ※番組HP https://www4.nhk.or.jp/P6172/2/
- 詳細
2020年3月1日,日本デジタルゲーム学会第10回年次大会で発表予定だった FishyFishy3 Advance, 学会は中止になりましたが,プロモーション動画はYoutube上で公開しました!FishyFishy3 Advanceは,これまでのバージョンと比べて大幅に学習機能を強化,iOSとAndroid版をリリースしました.皆さんの英語力にあわせて自動的に学習できる他,数日学習するとTOEIC換算で何点かを概ね当ててくれます!
- 詳細
「アジアデジタルアート大賞展FUKUOKA」は2001年から行われているデジタルコンテンツの国際コンテストで,デジタルコンテンツのクリエータ発掘・育成の場として世界に知られています.数理情報工学科の学生はこれまでも作品応募を行ってきましたが,このたび大学院1年生の齋藤憧弥君が「XyloStories」で学生カテゴリのエンターテインメント(産業応用)部門で初入選しました!おめでとうございます.XyloStoriesは子供音楽教室の先生を支援するためのシリアスゲームです.本作品は齋藤憧弥君がディレクタ及びプログラマとして制作したもので,4年生の湯原聖也君,山家弘大君がアーチストとして加わった他,H/W及び信号処理部の開発には杉沼浩司先生がアドバイサとして加わった他,シリアスゲーム制作全体の指導は粟飯原先生と古市先生が行った共同制作作品です.おめでとうございます!
- 詳細
会津若松市で「医療・福祉分野でのシリアスゲーム活用を考えるシンポジウム」が行われ,「ゲームのチカラと高齢者福祉への活かし方」という演題で粟飯原先生と一緒に講演を行うとともに,「ICTとシリアスゲームを活用し,会津で高齢福祉産業を生み出そう」というテーマでパネルディスカッションのモデレータを行ってきました.

会津若松市の人口は約12万人,高齢者率は31%を越える全国平均を上回る高齢者率の街です.会津若松市が抱えている高齢者福祉に関する課題はおそらく全国共通の課題.今回全国に先駆けてシリアスゲームの高齢者福祉をターゲットとした新産業化を考えようと,シンポジウムに多くの皆さんが集まりました,特に,会津若松市役所の健康福祉課と観光商工課の皆さんに加えて,地元で高齢者福祉施設を運営する皆さんが集い,その場で次々と意思決定ができたのはとても爽快でした.室井市長にもお越しいただいてシリアスゲームTANOを体験していただいたので,今後会津若松市はシリアスゲームの分野で大きな変化を起こせるのではないかと感じました.
私の講演の中では,ゲームのチカラを紹介した後,そのチカラを世の中の課題解決に活かすシリアスゲームについて紹介,続いてシリアスゲーム先進国のオランダが,この約10年でシリアスゲームを新IT産業として確立するに至った要因等を紹介しました.その中で最も大きいのは「市長ゲーム (Mayer's Game」ですが,次に大きいのは2014年から始まったアプライドゲームジャムです(オランダではシリアスゲームのことをアプライドゲームと呼ぶ).アプライドゲームジャムは,オランダと韓国でシリアスゲームの教育と国際化に関する政府間協定で実施されるようになったもので,半年毎にユトレヒトと浦項で行われているイベントです.日本からは2016年に粟飯原先生が初参加した後,日本大学からは毎年学生が参加しています.
- 詳細
数理情報工学科の古市研究室では人の行動を対象としたモデリング&シミュレーションの研究をしており,TVの歴史番組では戦国時代に起きた様々な史実をコンピュータ上で再現し検証するために用いられます,2019年12月には2夜連続でNHKの歴史番組に古市研究室の学生と教員が登場しました.
- 2019年12月18日(水)NHK総合22:30-23:20 「歴史探偵 本能寺の変」(新番組第1回目)
- 2019年12月19日(木)NHK-BSプレミアム 18:00-18:50 「風雲!大歴史実験 豊臣秀吉 天下人への秘策・大返しの真実」(2019年3月9日放送分の再放送が決定しました)

- 詳細
2019年12月8日(日)から第8回シリアスゲームジャムが行われ,15日(日)までの1週間で25人の学生と社会人が即席のチームを組んで5本のシリアスゲームが開発されました.古市研究室からは3名の学部3年生,数理情報工学専攻からは1名の大学院1年生が参加し,3年生の柯さん(ニックネームはりっちゃん)がデザイナとして参加したチーム「マーベル」の制作したゲーム「Telepathy」は最優秀賞(Grand Prix Award)とデザイン部門の優秀賞(Excellent Design Award)を受賞しました.また,大学院1年生の齋藤君(ニックネームはとうや)はリサーチ部門の優秀賞(Excellent Research Award)を受賞しました.おめでとうございます!

- 詳細
2019年12月8日(日)から第8回シリアスゲームジャムが開幕し,15日(日)までの1週間で各国から集まった学生と社会人が,「障がい者と高齢者と健常者が共通の土俵で競うことができるディジタルゲーム」を5本を開発中です.オリンピックの世界では,健常者と障がい者の大会は別々にオリンピックとパラリンピックとで実施されています.しかし,e-Sportsの世界では,近い将来障がい者と健常者とが同じ大会で競うことが実現するのではないかと考えられ,メンバが全員70歳以上のチームが活躍している例などもあります.第8回シリアスゲームジャムでは,バリアフリーな世界の実現に向けて,基調講演をしていただいた国立病院機構北海道八雲病院の田中先生,「健康笑顔リハビリ系」のシリアスゲーム開発で知られる(株)TANOTECHの三田村勉氏をはじめ,ユニバーサルデザイン専門家の榊原直樹先生等様々な関連分野の研究開発者が集まり,古市研究室のシリアスゲームの構築法に関する研究の輪は更にひろがりつつあります.
なお,古市研究室からは学部3年生が3名と大学院生1名が第8回シリアスゲームジャムに参戦しています.応援よろしくお願いします!2020年4月に古市研への研究室配属を目指している学生は,この中ようなシリアスゲームジャムに積極的に参加して他大学の学生やプロと交流したい学生を,積極的に受け入れます!

- 詳細
下記の通り,古市研究室では1,2年生向けに研究室見学会と配属説明会を開催します.数理情報工学科では3年の4月に研究室配属を行います.当日は,来年度及び再来年度古市研究室への入室を希望する学生向けに説明いたしますので,配属に興味のある1,2年生はできるだけ参加してください.事前申込み制ですが,申込み無しでの当日参加も可能です.なお,古市研究室の学部生は現在4割(22人中9人)が女子です.女子学生はもちろんのことですが,シリアスゲーム制作に興味のある男子学生にも多数集まっていただけると嬉しいです.また,配属希望者に向けての情報はこちらにも書かれています,参考にしてください.
記 日時:2019年12月18日(水)16:30~18:30 (入退室自由) 場所:23号館102室(古市研究室) 内容:・研究室の紹介と見学,eSports体験も含む ・2020年度と2021年度の配属説明会

- 詳細
同僚の見坐地先生から得た情報ですが,2019年12月1日,古市研究室有志の発案により研究室対抗で野球の試合以下の通り実施したとのことです. 今回参加したのは見坐地研究室,野々村研究室,髙橋研究室と古市研究室でした.第1試合は接戦でもあり白熱,第2試合は珍プレイもあり,とても面白く愉快な試合でした.また,伝統的に強いと言われている見坐地研究室は,今回も強さが最大限に発揮されたようです.普段あまり話す機会等がない学生同士親睦がはかられ,非常に盛り上がりました.今後も様々な機会で研究室の交流を図れればと思います.
・日時:12月1日 12:00~17:00 ・場所:実籾校舎第2グランド ・対戦チーム:古市・野々村研究室合同チーム VS. 見坐地研究室 ・試合結果: - 第1試合:1対1の引分け - 第2試合:9対2で見坐地研究室の勝利

- 詳細
今年の開催が8回目を迎えるシリアスゲームジャム,12月2日(月)正午まで参加申込みを受付中です!今回の実行委員長は数理情報工学科の粟飯原先生が務めます.生産工学部からの多くの学生の皆さんの参加を待ってます!詳細及び申込みはは以下のポスター画像をクリックしてください.なお,このポスターは古市研究室3年のRichelle Ngoさんが描いたものです.
日本デジタルゲーム学会(DiGRA JAPAN)ゲーム教育研究部会では,第8回「シリアスゲームジャム ~みんなのバリアフリー(3)」(略称SGJ8)を2019年12月に東京・立川の(株)ビサイドで開催いたします.SGJ8では,シリアスゲームで解決すべき課題としてゲームのアクセシビリティをテーマとし,障がい者や高齢者と健常者が同じ土俵で競うことができるデジタルゲームを3日間で制作します.ゲームのアクセシビリティに関する専門家(田中栄一先生)及び高齢者のリハビリ現場向けのゲーム開発専門家(三田村勉氏)の知識に,ゲーム開発者や社会人そして学生らの力を結集し,3日間でシリアスゲームを制作します.募集定員は35名と限りがあります,お早めに参加をお申し込み下さい.また,新聞,雑誌,TV等の取材も承ります,問合せ先までメール等でご連絡ください.
問合せ先: 日本大学生産工学部 古市昌一(このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。)

- 詳細
古市研究室の恒例となった東京ゲームショウ2019への出展,今年が3年目となりました.ビジネスデイの2019年9月12,13日に日本大学生産工学部のブース(オランダパビリオン内, ホール3, ブース番号C02)には100人を超す方々が訪れ,シリアスゲームと日本大学生産工学部の関係について知っていただくことができました.特に,ゲーム業界で活躍されている多くの日本大学の同窓生の皆様が立ち寄る場面も多く,日大が東京ゲームショウに出展しているのを知って驚かれていました.


- 詳細

国際会議DiGRA 2019 KYOTOが京都立命館大学で2019年8月6日(火)〜10日(土)に開催され,世界35カ国から400名を超えるゲームの研究者が集まり,シリアスゲームやゲーミフィケーション等ゲームの力を世の中の問題解決に応用する方法や,ゲームの芸術表現,eSports等ゲームの観戦と人との関係,知的所有系や法整備等,10のトラックに分かれて250の研究発表を行いました.参加者の中には女性研究者が非常に多く,また博士後期課程在学中の学生が多く,海外にはゲームで学位を取得する学生が多いのに比べて,日本ではゲームを学ぶ学生の多くが大学院へは進学しないという国の違いが大きく出たように思います.そのような事情の中,数理情報工学科の学生と教員はこの学会で次のような大きな役目を果たし,世界におけるデジタルゲーム研究における日本大学の存在感を大きくアピールできました.
- Nadia Groenewald (ユトレヒト芸術大学からの交換留学生 (2018年2月〜7月)) : DiGRA 2019のロゴ,ポスター等メインビジュアル全般のデザインを担当
- 齋藤憧弥君(大学院2年生):インタラクティブセッションで"Differences between M&S and Serious Games"というタイトルで発表,開発中のXyloStoriesをデモンストレーションしました
- 粟飯原萌先生(助手): DiGRA 2019のOrganizing Committee委員としてホームページの管理等を担当
- 古市昌一先生(教授): DiGRA 2019のProgram Committee委員として,500件を超える投稿論文に対して1,200人の査読委員を割り当てて採否を決定,プログラムを作成する業務を担当.また,粟飯原先生と共著の論文 "A Challenge of Developing Serious Games to Raise the Awareness of Cybersecurity Issues"を発表.
- 詳細
2019年6月10日(月)から8週間にわたって毎週月曜日に4時限連続(9:00-16:10)講義形式で行った「ゲームプログラミング及び演習」が,7月29日(月)に終わった.特に最後の2週間はゲームジャム形式(「習志野ゲームジャム」と命名」)で行い,全15チームが制作したゲームを外部リリースするところまでできたので,学生たちにとっては達成感が高かった講義だったのではないだろうか.特に,アジャイル型の開発手法であるSCRUMを全員が実践できるようになり,コストの見積もりとリスク管理の重要性を経験できたところが,今後社会に出た後のシステム開発に活かせる上では良かったのではなかろうか.

なお,途中6月24日(月)にはバイキング(株)の尾畑社長による特別講義を行っていただいた他,最終回の7月29日(月)にはバンダイナムコスタジオ(株)の大館氏と山田氏に来ていただいて3分の2程の作品を試遊していただけた点も,学生たちにとって刺激になったと思われる.来年度以降は,これまで以上に計画的に企業の方による特別講義の時間を盛り込んでいきたい.


- 詳細
2019年7月31日(水),日本大学部文理学部の宮田研究室と日本大学生産工学部の古市研究室との合同ゼミを実施しました.合同ゼミは,研究テーマが異なる研究室同士の学生が一同に介し,研究テーマを互いに紹介して意見を交わすことによってこれまで気づかなかったことに気づくとても良い機会です.今年1月30日(水)に生産工学部で実施した宮田研究室と古市研究室の第1回合同ゼミは,後期末だったこともあって研究発表形式で行いました.一方,今回は前期に行った各研究について途中段階で色々なアイデアを出すことを目的とし,ワークショップ形式で行いました.

今回合同ゼミを行った場所は 文理学部の本館1階にあるラーニングコモンズです.以下の写真を見ていただければわかるとおり,このようなゆったりとした勉強とワークショップを同時にできる明るいスペースは生産工学部にはありません.図書館とカフェと発表スペースが一つになっており,電球色の照明と昼光色の照明が効果的に配置されている,古市研究室の学生好みのスペースです.一方,生産工学部には自慢の未来工房があるので負けてはいませんが,生産工学部がkの両方を備えていれ,ば更に受験生が増えるのでは,との印象を持ちました.

ワークショップを実施するにあたり,事前に両研究室の大学院生が全部で6つのテーマを考えて各1枚のテーマ説明書の形式にして持ち寄りました.当日のワークショップではまず各チームが必ず両研究室のメンバが混在するように6つのチームに分かれ,チーム毎に異なるテーマが与えられて40分間のブレインストームを行い,その結果をチーム毎に発表する形式で進められました.また,ワークショップは2回行い,各チームは合計で2つのテーマについてブレインストームを行いました.

- 詳細
2019年6月29日(土)~7月1日(月)に中国・吉林省・長春の吉林動画学院(Jilin Institute of Animation)で開催されてた国際ゲームジャムで,日本代表として参加した数理情報工学科の3年生柯文筑さん(台湾の中国科技大からの交換留学生)が所属するチーム"Panda Eyes"が開発したゲーム"Hungry Panda"が最優秀賞(金賞)を受賞しました! 柯さんはチームで3Dモデラーを担当し、本ゲームジャム最多国数の4カ国混成の6人チームを、得意の英語と中国語でチームのまとめ役を果たしました。おめでとうございます.
なお,日本からはカプコンのゲームクリエイター(モンスターハンターのワールドディレクタ)徳田優也氏がゲストとして参加し,参加者に向けて講演を行いました.徳田氏とは帰国時にインチョンまで同じ飛行機となり,柯さんとはフィリピンのトカゲの話しがきっかけとなって古市先生と3人でゲーム会社への就職の話題で盛り上がりました.
 向かって一番左端が柯文筑さん,中央はYoon学院長
向かって一番左端が柯文筑さん,中央はYoon学院長
 向かって右から3番めはカプコンの徳田優也氏(モンスターハンターのワールドディレクタ)
向かって右から3番めはカプコンの徳田優也氏(モンスターハンターのワールドディレクタ)





- 詳細

- 詳細
2019年5月31日(金)午後,森永製菓が主催する商品企画コンテストの担当者の方が古市研究室を訪問され,学生からイノベーションのためのアイデアを引き出すための方策等について粟飯原先生を含めて情報交換しました.詳細は以下をお読みいただくとして,生産工学部の学生の皆さんが2,3人でチームを組んで応募をするのには絶好の機会ですので,応募を検討してみてはいかがでしょうか.
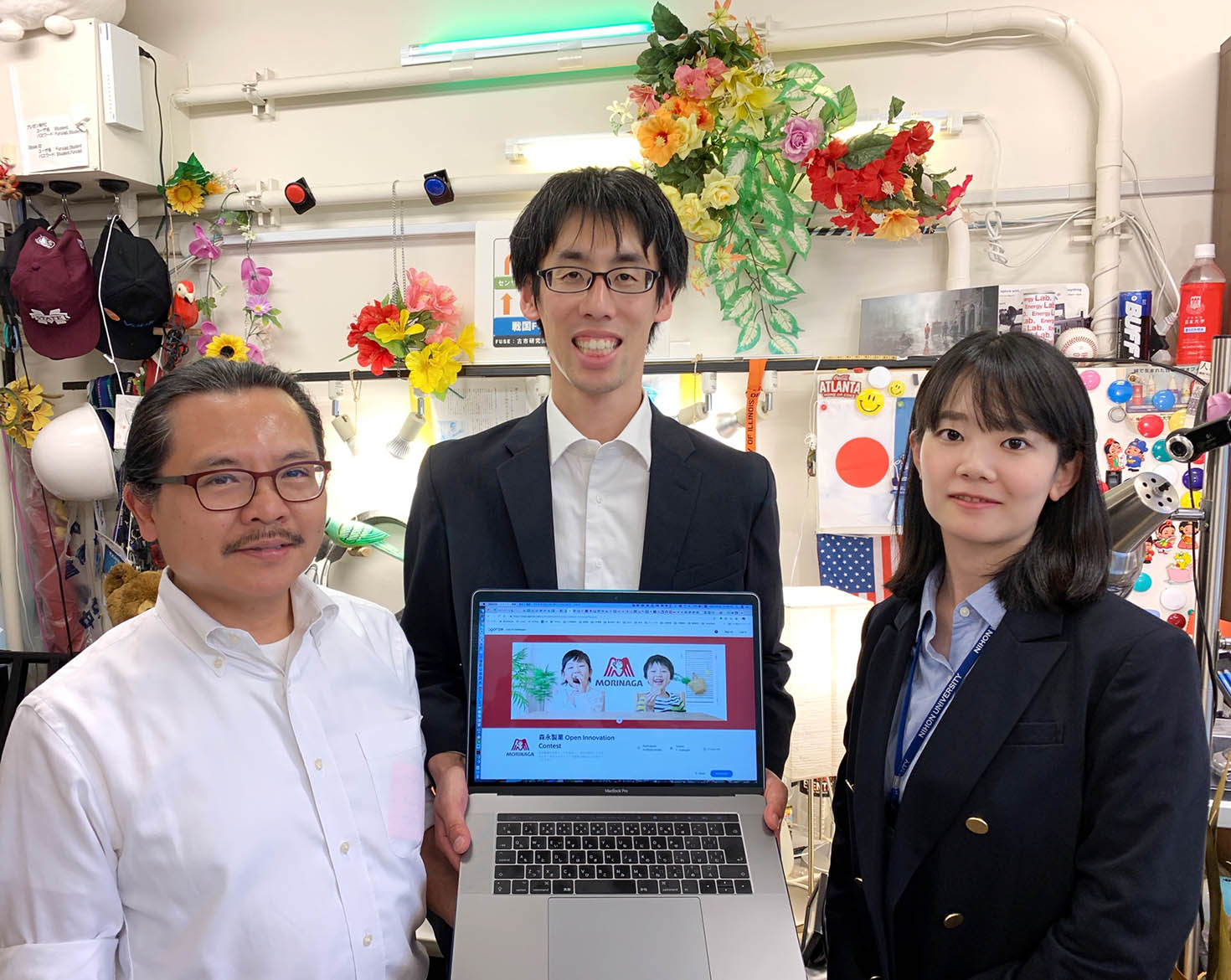 森永製菓オープンイノベーションコンテストをご担当の森永製菓(株)平野さん
森永製菓オープンイノベーションコンテストをご担当の森永製菓(株)平野さん
この商品企画コンテストは,"オープンイノベーションのためのオンラインプラットフォーム"として知られるagorizeを利用して森永製菓が実施しているもので,森永製菓の方はagorizeの担当者の方と一緒に来られました.
agorize上には世界中の様々な企業が世界中の学生や起業家等からアイデアを募集する「チャレンジ」が掲載され,本日現在募集されている11個のチャレンジのうちの一つが,森永製菓のものです.チャレンジには毎回世界中から多数の応募があるそうですが,今回森永製菓が募集するのは,日本の大学生及び大学院生からの応募を受け付けるものですので,食品工学・流通・応用分子化学・プロダクトデザイン・数理情報工学,そしてGloBEやEntre-to-BE等で日々学んでいる生産工学部の学生にとっては,絶好の機会です.